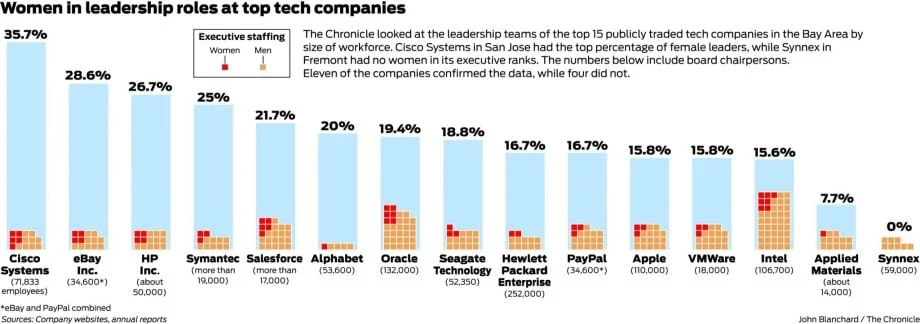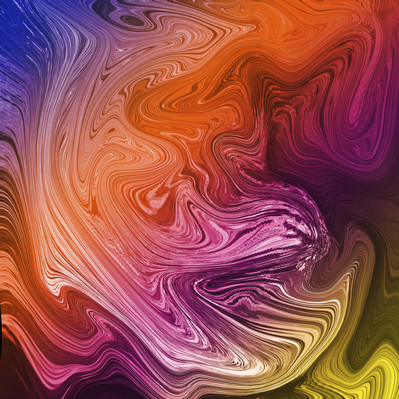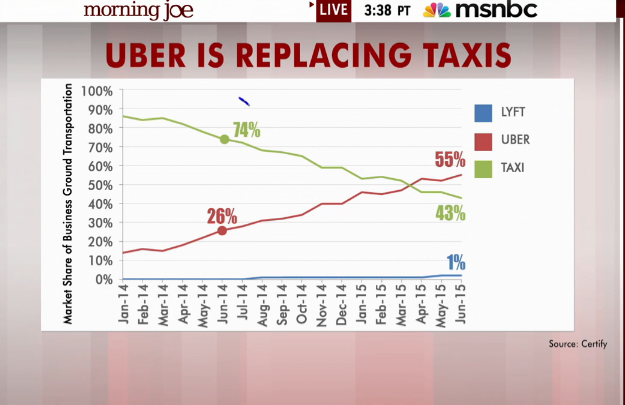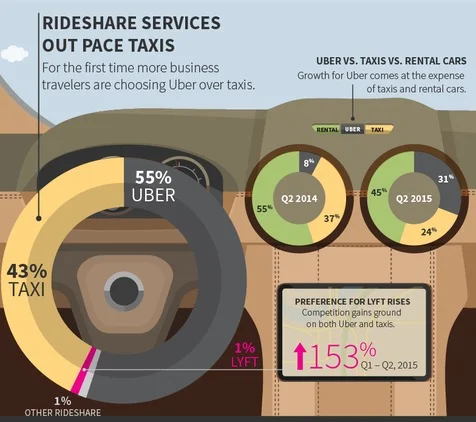もちろんこの2社のデータ改ざんの意味合いは異なる。三菱は、25年前から法令と違う測定方法を採用し、虚偽のデータを作り、消費者に対して燃費をよく見せるという行為を意図的に行ってきた。スズキ自動車の場合は、「テストコースは海の近くにあり、風の影響で計測結果にばらつきが大きいため、つい装置ごとの実測値を使ってしまった」と釈明して、意図的に燃費をよく見せるための不正ではないと主張している。ただし、両社とも一般消費者に、「虚偽=嘘」のデータを公表していたことは事実で、「見つからなければ、いいじゃない」といった日和見的態度で、長年経営者も含めて企業全体がこれを容認してきたように思う。
「空気を読めよ!」という集団における無言の圧力
この「見つからなければ、いいじゃない」というマインドセットは、Corporate Governance(コーポレート・ガバナンス)が正常に機能できない原因をつくる、最も不適切なAttitude(姿勢・態度)である。またこれは、日本の企業でよく見られる、あるいは暗黙のうちに実行される、企業内の人間が周囲の「空気」を読んで行動する特性と、符合する。「空気を読めよ」という無言の圧力は、日本ではさまざまな場で発生するが、企業内でこれが発生すると、例え「個人としてはこれは不適切あるいは不正である」と思っていても、周囲の圧力が強い場合はそれが言い出せず、「自社のためなんだ」という曖昧な納得の仕方で「見ないふり」をしてしまうことがある。この「見ないふり」は、そのうちそれが「不正」であったことを忘れさせ、「責任」の所在の曖昧さの中で、Accountabilityを問わない日本的な気質に、そのまま流れていってしまう。
Corporate Governance(コーポレート・ガバナンス)って何なんだ?
コーポレート・ガバナンスの定義は「株主、金融関係者、債権者、役員、社員」といった企業を取り巻くステークホルダー(利害関係者)が、企業活動を監視して、健全かつ効率的な経営を達成するための仕組み」である。欧米では1980年代に、企業の業績悪化や不祥事発生の原因が経営者の専制的な支配にあったという認識から、企業の統治を改善する動きが生まれた。ここから、企業の業務を執行する機能(マネージメント)と経営者の執行活動を監視する機能(ガバナンス)とを分離することが求められるようになった。日本でも2003年4月商法改正により、マネージメントとガバナンスを分離するための委員会等設置会社が認められるようになっている。
コーポレート・ガバナンスが有効に機能すると、ステークホルダーは以下のようなアドバンテージが得られる。
(1) 経営者の独走・暴走を株主がチェックでき、阻止できる
(2) 組織ぐるみの違法行為をチェックでき、阻止できる
(3) 企業理念を実現するために、全役員・社員の業務活動が方向づけられる
さらにコーポレート・ガバナンスを適切に機能させるには、以下の要素が必要となる
· 経営の透明性と健全性、および法令順守
· すべてのステークホルダーへのAccountabilityの徹底
· 迅速かつ適切な情報開示
· 経営者および各層の経営管理者の責任の明確化
· 内部統制の確立
以下はOECD Principles of Corporate Governanceによる説明で、上述の日本語とこの英語を比較しても大きな違いはない。
"Corporate governance involves a set of relationships between a company’s management, its board, its shareholders and other stakeholders. Corporate governance also provides the structure through which the objectives of the company are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance are determined."
Wikiには以下のようなCorporate Governance(コーポレート・ガバナンス)のPrinciplesが挙がっていた。
· Rights and equitable treatment of shareholders
· Interests of other stakeholders
· Role and responsibilities of the board
· Integrity and ethical behavior
· Disclosure and transparency
この英文で出てくる「Integrity」と「Ethical Behavior」は重要なキーワードで、Peter Druckerはこの「Integrity」は、経営者にとって最も重要な資質として挙げている。また、これは学ぶことができにくいもので、あえて日本語訳すると「真摯さ」となる。彼はこの資質に関して、「部下たちは、無能、無知、頼りなさ、不作法など、ほとんどのことは許す。しかし、真摯さの欠如だけは許さない。真摯さに欠ける者は、いかに知識があり才気があり仕事ができようとも、組織を腐敗させる。」という。
「倫理と道徳」の両輪があってこそ、集団における「コーポレート・ガバナンス」は機能する
また、私があえてここで「Integrity」と一緒に重要視したいのは「Ethical Behavior」である。この場合の「Ethical」は、日本語で「倫理」あるいは「道徳」と訳されることがあるが、この場合は「倫理および道徳的的な行動」と2つを同列に持ってきて訳すべきだと思う。理由は簡単で、以下に挙げるブログ「生きる道草」による「倫理」と「道徳」の意味の違いを考えれば、よく理解できる。
· 倫理:社会集団の規範
· 道徳:普遍的な人としての心のあり方
例① 倫理は、「嘘をつけば人として信用されなくなるから、嘘をつくべきではない」と規範の正当性を大切にする。
例② 道徳は、「人を騙すのは良くないので、嘘をついてはならない」と人としての道を示す。
· 道徳だけでは、本当に正しい事なのかを検証出来ないので、倫理によって、その正当性を考える必要がある。よって、道徳と倫理が二つとも備わっていなければ、意味がない。
· どんなに良い行いをしても、その動機が不純であれば、道徳が欠けており、どんなに悪い行いをしても、悪意や身勝手さが無ければ、倫理が欠けていると定義出来る。
上述した三菱自動車の不祥事は25年という長期間、さらにそれ以外にも三菱自動車は度々リコール隠し問題などを発生させており、完全に人としての道を示す「道徳(=個人)」も、集団としての規範の正当性を大切にする「倫理(=集団)」も欠落している。すなわち、完全にコーポレート・ガバナンスが停止している企業といえる。
車を運転するということは「死」と向かい合うこと
自分が長年ビジネスで自動車製造メーカーの商品企画に携わっているせいか、生活における「車」というもののPro & Conを真剣に実感している。公共交通機関が整っている日本と違い、常に車を運転する状況に直面するアメリカにおいて、「車」の持つ意味は大きい。「車には人の命がかかっている」、自分が運転しなくても、歩いているだけでも事故死する可能性は大いにある。燃費の不正データは、人によっては「たかがちょっとした数字の違いだろう」と言う人もいるが、「不正」は「不正」であり、それは「虚偽=嘘」で、こういう「虚偽」を黙認してきた企業は、経営者も含めて企業そのものに「Integrity(真摯さ)」が欠落している。それは実に恐ろしいことで、そうした企業に「命を預ける車」を製造してもらっては、いけない。また、そうした不正を防止するための「コーポレート・ガバナンス」が、単なる綺麗ごとのお題目であってはならない。経営トップから製造にかかわる現場の1人1人まで、この重要なPrinciplesである「Integrity and ethical behavior」の認識を持ち、「道徳と倫理」という2つの両輪に支えられた意識を持つ必要がある。
「空気は目に見えない、すなわち読めるものではない。空気は人が生きるために吸うものである。」そんなことを思わせる、昨今の自動車業界の不祥事である。まずは本質的な部分の認識から始めるべきではないかと思う。